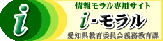|
最新更新日:2024/06/11 |
|
本日: 昨日:191 総数:283768 |
いつもにっこり大野小!
1月20日〔月〕 月曜朝会「あいさつで元気に」



それは何か? クイズを出したいと思います。 数えてはいませんが、「半分くらいの人ができていて、半分くらいの人ができていないことです」「できている人も、できているときと、できていないときがあります」―それは「あいさつ」です。 皆さんには、少し厳しい言い方になりますが、あいさつができないことで、「悲しい」思いをしている人がいます。朝や帰り、皆さんの登下校の安全のために立ってくださっているお家の人、一緒に付き添ってくださっている方から「あいさつしても、あいさつが返ってこないので悲しい」という声を聞きます。校長先生も登校の様子を見に行った時、同じように感じます。始業式に「日本一みんなにっこり大野小」となるようにという話をしましたが、これは大野小の子どもたちだけでなく、大野小の地域に住んでいる全ての人がということです。 よく「あいさつをしましょう」と言いますが、校長先生は「あいさつはしなければならないもの」と思っています。また、「ひと」を大切にしてほしいという話をしていますが、「悲しんでいる」ということは、その人を大切にしていないということです。悲しい思いをする人がいないようにしてください。皆さんのあいさつは相手の人を元気にします。必ずあいさつをしてください。 ここまでの話を聞いて、「ぼくは、私は、あいさつをしているよ」という人もいると思います。できている人は、もちろん続けてください。でも中には、しているけれど、残念ながら相手に伝わっていない「あいさつの仕方」になってしまっている人もいます。 では、よく相手によく伝わるあいさつの仕方はと言うと、それは「大きな声で」「相手の顔を見て」「自分が先に」です。特に「相手の『右目』を見て、あいさつをする」とよいようです。 高学年の人は、低学年の人のお手本になってください。朝の登校のときも、高学年の人がしっかりあいさつできる班は、低学年の子からも元気のいいあいさつが返ってきます。 ここにいる一人一人、全員がよく考えてください。学校内で、そして登下校や学校外で、あいさつの声が聞こえて、この「大野小学校の地域の人たちがみんな」元気な気持ちで生活できるといいなと思います。 1月12日〔日〕 常滑市消防出初式





今年は消防署や消防団の方たちに加えて、小倉区の防災班も参加し、小倉の区長さんが参加した市内4区の指揮者を担当していらっしゃいました。 あいにくの曇天だったため、一斉放水が青空に映えてというわけにはいきませんでしたが、凛とした分列行進に気持ちが引き締まりました。 西本PTA会長さんも旗手を務めていらっしゃいました。 1月11日〔土〕 大野小おたすけ隊(花の苗の植え替え)

卒業式・入学式にきれいな花が見られるのが楽しみです。大切に世話をしていきたいと思います。 「また、声をかけてくださいね。」とおっしゃって帰られる皆さんの姿を見て、心が温かくなりました。ありがとうございました。 3学期始業式の話



楽しかった冬休みも終わりましたが、休みの間、大きな事故やけがなどもなく、みんな元気で3学期を迎えることができ、本当によかったと思います。 さて、今日から3学期が始まりますが、3学期はたいへん短く、学校に来る日がおよそ50日しかありません。そんな短い3学期に、皆さんに考えてほしいことを話します。 それを書き初めで書いてみました。これ(襷)です。難しい字ですね。「たすき」と読みます。「襷」は、元々は日本の服を着たとき、袖などが邪魔にならないように縛るための紐や布のことですが、皆さんがよく知っているのは、チームで走って競走するときに順番に渡していく、肩から斜めにかける布だと思います。大野小の運動会ではアンカー襷として使っていました。 チームで競走して襷を渡していく競技を「駅伝」と言います。観た人もいると思いますが、1月2日と3日に箱根駅伝が行われました。箱根駅伝は、1チーム10人で1人が約20km(常滑市の北南より長い距離)を走り、その10人が襷を受け渡して東京と箱根の往復217.1kmを21の大学やチームが競争する大会です。1チーム10人もいるので、全員がよい調子で走れるとは限りません。優勝したのは青山学院大学ですが、青山学院も1人目の選手は7位でした。逆に、1人目の選手は1位でも、最後は9位というチームもありました。でも、走ることができなくなったり、あきらめたりすることなく21チームの全ての選手が力を出し切り、襷を次の人に渡してゴールすることができました。きっと襷と一緒に、一人一人の「思い」も受け渡していったのだと思います。 「襷を渡す」ことを「襷を繋ぐ」とも言って、物事を次の人へ受け渡すという意味もあります。実は「目に見えない襷」がいっぱいあって、私たちはその襷をつないでいます。 その一つに干支があります。去年は何年でしたか。「亥年」ですね。今年は、「子年」です。干支の「亥」には、「勇気」や「冒険」という意味があると言われています。干支の「子」にも「行動力」という意味があると言われています。干支の「亥」も「子」に「がんばれ」という思いを込めて襷を渡したと思います。 この大野小にも、皆さんが「受け取った襷」、そして「渡さなければならない襷」があります。それは、「伝統」という襷です。「伝統」というのは、昔からずっと受け継がれてきた「こと」です。大野小で受け継がれてきた「こと」は何でしょうか。いくつかあると思いますが、間違いないのは、校訓の「和して進む」ということです。そして、「日本一みんなにっこり大野小」になるようにすることです。 ただし、それは何もしないで「みんなにっこりしなさい」という意味ではありません。みんなが気持ちよく生活できるように「思いやり」の気持ちをもって生活してにっこりするのはもちろん、がんばって「勉強や努力」をして、少しずついろいろなことができるようになってにっこりする、病気やけがをしないで「元気に」過ごしてにっこりすることができるようにするということです。「和して進む」「日本一みんなにっこり大野小」は、これまで卒業した人たちが大切にしてきた伝統です。 大野小は間もなく満60歳。4月からは61年目になります。皆さんには、「60年間の伝統の襷」を大切にし、4月からの大野小に受け渡してほしいと思います。特に6年生は、5年生から1年生の「お手本」になってがんばってほしいと思います。1年生は、4月に大野小に入ってくる子たちのお手本になれるように、他の学年も胸をはって今の自分たちの「学年の襷」を次の学年に渡せるようがんばってください。 それでは、短いですが中身の濃い3学期にしましょう。 2学期終業式の話(番外編)





なんと、今年の年末は日食がありました。12月26日(木)この地方(名古屋)では、かけ始めが14時25分、最大が15時30分、終わりが16時33分ということです。ただし、残念ながら天気が良くなさそうです。でも、たいへん勉強になりました。 ※写真は2012年05月21日の金環日食の時に撮影したものです。今回は部分日食です。 ※目を痛めるので、太陽を直接見てはいけません。 ※以下は、国立天文台のホームページの注意書きです。 「日食とは、月が太陽の前を横切るために、月によって太陽の一部(または全部)が隠される現象です。太陽は、たいへん強い光と熱を出している天体です。そのため、肉眼で直接太陽を見ると、たとえ短い時間であっても目を痛めてしまいます。太陽が欠けていても、また、地平線に近づいて光が穏やかになったように感じても、光と熱が強烈であることは変わりません。安全な方法で観察しなければ、最悪の場合は失明する危険性があります。日食グラスなど専用の観察器具を正しく使って、安全な方法で日食を観察してください。」 2学期終業式の話



今日で2学期が終わります。そして、令和元年もあと少しになりました。令和元年、2学期を振り返り、新しい令和2年を迎えるにあたって2つお話ししたいと思います。 まず、1つ目です。2学期の始業式に、失敗してもいいので、積極的にやってみる、「トライ」するということ、それから「命・自分・友達」を大切にして、力を合わせて取り組んでほしいという話をしました。皆さん、できたでしょうか? まず「命」については、少しけがが多いのは気になりましたが、命にかかわるような大きな事故やけがもなく、今日の終業式を迎えることができて、よかったと思います。 「トライ」すること、「自分・友達」を大切にして、力を合わせるということについてはどうでしょう? 校長先生は「運動会」が印象に残っています。今年は赤組が優勝しましたが、赤組も白組も全力で競技をし、失敗してもあきらめずがんばっていました。部活動もがんばっていましたね。運動会も部活動も、ラグビーのワールドカップに負けないくらいがんばりました。そして、どちらも心を込めて、友達を応援していました。「学習発表会」も印象に残っています。自分もがんばり、そして友達を助け、力を合わせて取り組む姿がたくさん見られ、素晴らしい発表や演技をすることができました。2つの大きな行事だけでなく、社会見学や毎日の学校での勉強でも同じようにがんばる姿がたくさん見られました。みんな2学期に、ひと回り大きくなったと感じます。 2つ目のお話です。もうすぐ新しい年、令和2年になります。1年が終わって、新しい年になる「年末年始」にはいろいろな行事や昔から行われていること(習慣)があります。そこで、年末年始に関係するものの形を集めてみました。 1番から6番までありますが、何の形でしょう。皆さんに、聞いてみたいと思います。 1番は、クリスマスのクリスマスツリーです。 2番は、鏡餅です。年神様がやってきて寄りつくところ(居場所)で、私たちがその餅を食べることで年神様から力をもらうと言われています。 3番は、12月31日の大晦日に食べる「お蕎麦」のどんぶりです。お蕎麦は細くて長いので、細く長く健康に暮らせると言われています。 4番は、お寺の鐘、除夜の鐘です。除夜の鐘は108回鳴らされます。人間には人の心を迷わせたり、悩ませたりする元になるものが108あって、大晦日に108回鐘を鳴らして、それを一つ一つ取り払うと言われています。 5番は、太陽、初日の出です。6番は、はがき、年賀状です。 5番、6番は、ほかにもあります。何の形かというと、お餅の形です。お正月には、お雑煮を食べるお家が多いと思いますが、皆さんのお家のお餅の形はどちらでしょう。 丸餅○の人?、角餅□の人? 隣の人となぜ違うのでしょう? あとでお家の人に聞いたり、自分で調べたりするとおもしろいと思います。 年の終わりと初めに関するものはまだまだあります。先ほど話したものも、違う説もあるかもしれませんが、それぞれ大事な意味がありますので、ぜひ知ってほしいと思います。そして何より、この一年無事に過ごせたことに感謝気持ちをもってほしいと思います。 それでは、けがや病気をしないで、また交通事故にあわないで、冬休みも「いのち」「自分」「友達」大切にして、そして「トライ」して、よい冬休みにしてください。1月に皆さんの元気な笑顔にまた会えることを、校長先生は楽しみにしています。 12月2日〔月〕人権講話 「同じ」を大切に、「違う」も大切に…



まず、「人権」というのは何でしょうか? 「人権」とは、「人が安心して生きていくために大切なもの」です。「人権を守る」というのは、「みんなが毎日安心して生活できるようにする」ということです。そのためにはどうしたらよいでしょうか? それは、いつも言っている「自分を大切にし、他の人も大切にする」こと。別の言い方をすると「人の体や心を傷つけない」ということです。そこで、お互いを大切にすることができるように、「違うけれど一緒」というお話をしたいと思います。 皆さんの手のひらを見てください。皆さんの手のひらの模様は、隣の人と同じですか? 大きさはどうでしょう? 体の大きさはどうでしょう? 顔は、どうですか? 姿や形が同じ人は絶対にいませんね。でも、同じところがあります。今から確かめてみたいと思います。3本指をそろえて、頬っぺたの下の首のところを横からそっと押さえてみてください。ドキドキしていませんか。それは、皆さんの心臓が一生懸命に血液を頭(脳)に送っている「しるし(証拠)」のドキドキです。それは生きている、大切な「命」が皆さんの体の中にあるというしるしです。それはここにいる全ての人が「同じ」です。友達のドキドキも確かめてほしいと思います。みんな姿や形は違うけれど、命の重さは同じです。「誰かの命が重くて、誰かが軽い」「誰かが上で、誰かが下」ということはありません。人として「同じ」ということを意識して、そして「違い」も大切にして、お互いに大切にしてください。 もう一つ。ここにいる人は「全員大野小学校の児童です。仲間です。」体育館の後ろにある【日本一みんなにっこり大野小】という言葉。これは、大野小のみんなが「自分も、他の人も大切にするからにっこり」という意味です。 みんながにっこりするためには、当然、叩いたり、蹴ったりして人を傷つけてはいけません。嫌な気持ち、悲しい気持ちになることを言ってはいけません。間違っても「死ね」という言葉や「きもい」「うざい」などの言葉、人が嫌がる「あだ名」なども言ってはいけません。また、人が嫌がること、例えば「人の物に落書きする」「人の物を隠す」ということもいけません。当たり前ですが「いじめ」は絶対にいけません。嫌なことを言われた人、された人、いじめられた人の「心は傷つき、血を流します」。人の「心の痛み」が分かる人になってください。 「自分も、他の人も大切にする」。大野小学校の皆さん、そして皆さんだけでなく、世界中の人が安心して生きていけるように、自分も含めたすべての人を大切にしてください。 11月18日〔月〕朝会「一人も事故に遭わないことを願って」



でも、そういう話ばかりできるといいのですが、今日は「心配な話」「残念な話」をしなければなりません。少し前に、朝の放送で、学校に来るときに追いかけっこをして車の前に飛び出した人がいるという話をしました。今からも交通安全について、大事な話をしたいと思います。交通安全は車だけではありません。いつもより長い話になりますが、しっかり聞いてください。 この「看板」(写真)を見たことがあるでしょうか。この「踏切」(写真)のところにあります。実は、この踏切では、昔たいへん「悲しい事故」がありました。青海中学校の生徒が、電車との事故で亡くなっているのです。 今でもはっきり覚えていますが、39年前、校長先生が高校2年生の夏、ボーイスカウトのキャンプで数日間出かけていたときのことです。もともとこの踏切には、警報器しかありませんでしたが、キャンプから帰って来ると、黄色と黒の鉄の棒が「4本」立てられ、自転車では通れなくなっていました。理由を聞くと、中学生が電車との事故で亡くなったとのことでした。 どのような事故だったか。校長先生が聞いた話では、自転車の中学生は電車が通過するのを待っていて、1本電車が通過したので、大丈夫だろうと思って渡ろうとしたところ、すぐに反対側から電車が来て、事故に遭ってしまったとのことでした。年齢から考えると、皆さんのお父さんやお母さんの知っている人、友達だったかもしれません。でも、今日はその中学生が良くなかったという話をするわけではありません。 実は、校長先生も、小学生のとき、この踏切で、「うっかり同じこと」をしてしまったことがあります。当時、大野町の駅前にあったパン屋さんに、校長先生のお父さんと自転車で出かけるときのことでした。校長先生のお父さんが先に踏切を渡ったところで警報器が鳴ったので、校長先生は踏切を渡るのを止めて待っていました。しばらくすると、電車が来て通り過ぎたので、何も気にせず、左右もあまり見ず踏切を渡ってしまいました。ところが、まだ反対側から電車が来るため、警報器は鳴り続けていました。たまたま電車は来ておらず、事故にはならずに渡ることはできましたが、校長先生のお父さんから、滅茶苦茶(あえてこの言葉を使いました)叱られました。そのまま出かけましたが、帰って来るまで、校長先生のお父さんは何もしゃべってくれませんでした。今思えば、「それだけ危険だった」のだということを伝えたかったのでしょう。 実は、この大野小学校の近くにある踏切は、1本電車が通り過ぎても、すぐに反対からもう1本来るという、「すれ違いが、たいへん多い踏切ばかり」です。だから、このような看板が立てられているのです。また、事故の後に、当時の大野小学校や青海中学校の先生、地域の方たちが「心配して」、自転車で通れないように、鉄の棒・柱を立てたと聞きました。今は、「遮断機」もついたため、自転車も通れるように、鉄の棒が3本になっていますが、すれ違いが多いのには変わりがありません。 電車のスピードも速くなっています。皆さんは大野町の駅から常滑の駅まで、速い電車は何分くらいで行ってしまうと思いますか。校長先生は計ったことがありますが、距離は5km位あると思いますが、なんと「3分」です。通学路を走っている車より、かなり速いです。 今日この話をするのは、渡るときに気をつけないといけない踏切なのに、先週残念ながら、踏切のところで遊んだり、電車にとても近いところに立ったり、遮断機を触ったりして、ふざけている人がいるという話を聞いたからです。あってはならないこと、絶対してはいけないことです。踏切のところで遊んだり、ふざけたり絶対にしないでください。 「皆さんの、大事な命を、大切にしてください。」 もしも危ないことをしている人、危ないことに気づいていない人がいたら、周りの人で注意をしてください。地域の人にも、危ないときは注意をしてくださいと、お願いをしておきます。 でも、一番大切なのは、1年生も6年生も、学年関係なく、「一人一人がよく見て渡ること」です。そして、「もし注意をされたら、気づいてやめること」です。これは、道路を歩くときも同じです。 「皆さんの、大事な命を、大切にしてください。」 長くなりましたが、皆さんが、「絶対に、一人も事故に遭わないこと」を願っています。 10月21日〔月〕朝会 「地域で暮らす 地域とつながる」



また、朝会では話していませんが、私自身この地域の出身で、現在は名古屋市在住ですが、名古屋の地域の祭りで近隣の方々と知り合うことで、「地域で生きていること」と「安心」を実感しました。地域で暮らしている子どもにも大人にも、地域とのつながりは「大きな安心」になると考えています。そして、その地域は「大切なふるさと」になっていきます。「ふるさと」はいくつあってもいいと思います。子どもたちにとって、この「大野」のまちが、「大切なふるさと」になったらいいなと思います。 10月20日〔日〕大野地区防災訓練



体育館のフロアでは実際の避難所の間仕切りがされ、また体育館前では炊き出しが行われていました。これまで報道でしか目にしなかった光景を見て、「いつか必ず来る地震災害」について、改めて考えていかなければならないと強く感じました。 地域の力を感じて





また、9月22日(日)には、常滑市消防団消防操法大会に来賓として出席しました。「青海分団1班」の団員が、きびきびと行動する姿を見て、たいへん頼もしく思いました。(校長:齋田強一) 2学期始業式の話



1学期の終業式、夏休みに皆さんが使える時間は「660」時間、たくさんの時間があるので、いろいろなことに「挑戦」「チャレンジ」してほしいという話をしました。きっと一人一人素晴らしい夏休みを過ごし、思い出もできたと思います。校長先生は、5年生のキャンプがとてもよい思い出になっています。どの子も一生懸命自分で考えて行動していて、素晴らしいキャンプでした。さすが高学年ですね。 さて、皆さんはこのマークを見たことがありますか? ラグビーというスポーツを知っていますか。これは、今月9月20日から日本で行われるラグビーワールドカップ2019日本大会のマークです。今から、そのラグビーのことで2つお話ししたいと思います。 1つ目は「トライ」という言葉についてです。ラグビーのルールでは、相手のゴールの線を越えて、ボールを地面につければ「トライ」となって得点が5点入り、さらにボールをキックしてゴールに入れると2点もらえます。今、言った「トライ」という言葉には、「やってみる」「努力する」という意味があります。「挑戦」や「チャレンジ」と同じような意味があります。 皆さんは、「成功」の反対は何だと思いますか? 校長先生は「成功」の反対は、「失敗」ではないと考えています。失敗しない人はいません。失敗してもいいです。失敗したということは、上手くいかない方法が分かったということです。失敗したら、次にどうすればいいか、考えればいいです。では、「成功」の反対は何かと言うと、「何もしないこと」だと思います。2学期には、勉強はもちろん、運動会や学習発表会などいろいろな行事や活動があります。ぜひ、いろいろなことを積極的にやってみる、「トライ」するということを大切にしてください。 2つ目です。ラグビーワールドカップは、愛知県の豊田市でも行われるので、見に行くという人もいるかもしれませんが、大会は日本全国の12の会場で行われます。その会場の一つに、岩手県釜石市の鵜住居復興スタジアムがあります。実は、釜石市のスタジアムの場所には、もともと鵜住居小学校と釜石東中学校の校舎やグランドありました。ところが、2011年の東日本大震災の地震の津波により2つの学校とも壊されてしまいました。 皆さんに知っていてほしいことがあります。それは、東日本大震災の地震が起こったとき、釜石市には約3,000人の小中学生がいましたが、学校だけでなく、家にいた子どもたちも含めて、先生や友達、そして自分たちで考えて高いところに避難して、ほとんど全員が助かったということです。釜石市全体では、住んでいた約40,000人のうち約1,000人が亡くなったり、行方が分からなくなったりしているのにです。 なぜ、ほとんどの小中学生が助かったのでしょう? それは、防災学習や避難訓練をしっかりやっていたからだと言われています。今日は、大野小でも避難訓練を行います。皆さん全員が大事な命をもっています。皆さん一人一人は、世界に一人のかけがえのない存在です。それは友達も同じです。大事な命を守れるよう、真剣に訓練をしてください。また、普段の生活でも、自分を大切にし、友達も大切にしてください。大野小の校訓は「和して進む」です。2学期もお互いを大切にし、いろいろなことに友達と力を合わせて取り組んでください。 2つ話しました。1つ目は、いろいろなことに「トライ」してほしいということ。2つ目は、「命・自分・友達」を大切にしてほしいということ。いい2学期にしましょう。 1学期終業式の話
おはようございます。今日で1学期が終わり、明日から長い夏休みです。
その夏休みについて、今から2つお話をします。 1つ目です。これは何の数字かわかるでしょうか。 「660」今年の夏休みは44日間 1日9時間寝る人が起きているときに使える時間 「365」6年生の人の1学期のおよその授業の時間数(1年生:約320時間) どちらもだいたいの数ですが。夏休みにみなさんが使える時間がいかに多いかがわかると思います。夏休みは、普段と比べて「自分で使える時間」がたくさんあります。時間をどのように使うかは、皆さんたち子どもに限らず、大人になってもとても大切です。 「一日中、勉強をする」「一日中、遊ぶ」「一日中、テレビを見る」「一日中、お手伝いをする」「一日中、寝ている」……。一つ一つは意味のあることですが、「一日中」はできないと思います。一日の中に、それぞれがバランスよく入っていることが大切です。時間を「上手に」使える人は、いろいろな力を伸ばし、いろいろなことができるようになります。夏休みはいろいろなことに取り組めるすばらしい時間です。のんびりしているだけではもったいないです。ぜひ、いろいろなことに「挑戦」「チャレンジ」してほしいと思います。 2つ目です。2つめは、その夏休みに挑戦、チャレンジしてほしいことについてです。 1学期のスマイルタイムで、図書委員会が発表したときのことを覚えているでしょうか。 その発表の中で、今年の「課題図書」について、お薦めの本の紹介がありました。実は、その発表を聞いてから、お薦めの本のことがずっと気になっていました。そこで、この間の3連休に、低・中・高学年の部で気になった本を1冊ずつ読んでみました。 低学年の部で読んでみたのは、「心って どこにあるのでしょう?」です。 実は、このお話を作った「こんのひとみ」さんは、この本以外にもたくさんお話を作っていて、いいお話がいっぱいあります。私は、中でも「かあさんのこもりうた」「くまのこうちょうせんせい」というお話が大好きで、直接「こんのひとみ」さんと会える機会があったので、出かけて行って、お話をさせていただいたこともあります。 中学年の部で読んでみたのは、「そうだったのか!しゅんかん図鑑」です。 私は、理科(自然科学)が大好きなので、どんな写真が見られるかとてもわくわくしながら読みました。今まで自分の目で実際に見たことがあるはずなのに、見えていなかった「瞬間の写真」がいっぱい載っていて、自然科学やカメラのすばらしさを感じました。 高学年の部で読んでみたのは、「ぼくとニケ」です。 最近、私の家の庭に黒い子猫がよく来るので、気になって読みたくなりました。どんなお話か、ここでは話しませんが、「命」について深く考えることのできる本です。正直に言えば、お話の終わりで涙が流れました。この本に「出会えて」よかったと感じました。 夏休みは長いです。課題図書に限らず、ぜひいろいろな本を読んでみてください。 それでは最後に、長い夏休みに「挑戦」「チャレンジ」するのも、「読書」「本を読む」のも健康であってこそできることです。健康でこそ勉強や運動もできるし、楽しい夏休みになります。けがや病気をしないように、そして交通事故にあわないようにしてください。9月に皆さんの元気な笑顔に会えることを、校長先生は楽しみにしています。 



遠く離れていても 「ともだち」
5月20日〔月〕〜6月4日〔火〕に、中国からの派遣団(児童5名・引率2名)を迎え交流をしました。約2週間、子どもたちはさまざまな授業や給食・清掃などの学校生活を通して、お互いの文化について学び合ったり、触れ合ったりしました。2週間の交流の中で感じたことを、大切にしてほしいと思います。
交流にあたり派遣団から贈り物(中国の古詩:写真の右の書)をいただきました(写真の左の絵は中国の国花の「牡丹(ぼたん)」)。書かれていることを調べてみると、「海内存知己 天涯若比鄰」(海内(かいだい)知己(ちき)を存(そん)せば、天涯(てんがい)も比(ひ)鄰(りん)の若(ごと)し)と読むことがわかりました。「広い世界に親友がいれば、遠く離れていても近くにいるのと同じ」というような意味のようです。国際交流に相応しい、とてもいい「ことば」をいただいたと思うと同時に、「漢字」の奥深さを感じました。 以下は、それぞれの言葉(漢字)の意味です。 「 海内存知己 」 海内(かいだい)知己(ちき)を存(そん)せば ・海内…四海の内。天下。広い世界。 ・知己…自分を真に理解してくれる人。親友。 ・存 …いる。存在する。 「 天涯若比鄰 」 天涯(てんがい)も比鄰(ひりん)の若(ごと)し ・天涯 … 空の果て。 ・比鄰 … となり近所。 【原文】 中国の古詩(漢詩)の「杜少府之任蜀州」(王勃)で、読み方は「杜(と)少府(しょうふ)、任(にん)に蜀州(しょくしゅう)に之(ゆ)く」とのこと。 城闕輔三秦 風烟望五津 與君離別意 同是宦遊人 海内存知己 天涯若比鄰 無爲在岐路 兒女共沾巾 

令和元年がはじまりました

「 安心・夢・感動 」 本年度は44名の新入生を迎え、全校児童数252名でスタートしました。252名の子どもたちはもちろんですが、保護者、地域の皆様方の「安心・夢・感動」も大切にしたいと考えています。 <安心>という言葉から思い浮かぶのは ・安全 ・信頼 ・つながり ・居場所 ・見通し ・自己存在感 ・自己肯定感 ・誠意 ・スピード ・きれい ・できる状況づくり ・自信 ・励まし ・守られている ・見てくれている ・整った環境 ・「わかったよ」「できたよ」「たのしかったよ」など <夢>という言葉から思い浮かぶのは ・希望 ・目的 ・目標 ・ねらい ・楽しみ ・思い ・願い ・憧れ(先生・大人・上級生) ・伸びたい(伸びてほしい) ・できるようになりたい(なってほしい) ・わかるようになりたい(なってほしい) ・あんな人になりたい(なってほしい)など <感動>という言葉から思い浮かぶのは ・感動 ・やった ・できた ・わかった ・楽しい ・好き ・喜び ・悲しみ ・充実感 ・達成感 ・一体感 ・出会い ・別れ ・悔しさ(がんばったからこそ) など いろいろ思い浮かぶと思いますが、何よりも日々の「『小さな』 安心・夢・感動」を大切にしていきたいと思います。 校長 齋田強一 |
常滑市立大野小学校
校長 小林 哲子 〒479-0866 愛知県常滑市大野町10-70 TEL:0569-42-1011 FAX:0569-43-7268 ☆ご意見・ご感想をお寄せください
ohnosho@tac-net.ne.jp |
|||||||||